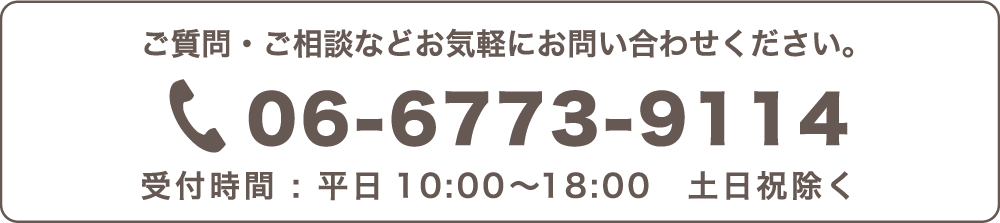【論点】訴訟物と実務1(訴訟物の論争)
2025/04/05 更新
旧訴訟物理論
(1)訴訟物とは、裁判における審判の対象のことである。
(2)旧訴訟物理論は、実体法の権利(個々の請求権や(形成原因ごとに別々に反省する形成権)ごとに訴訟物を構成すると考える。
新訴訟物理論
(1)新訴訟物理論では、請求権競合の事案において、給付を求める法的地位(受給権)を訴訟物と考える。
(2)請求権が競合しない事案では、新訴訟物理論でも旧訴訟物理論でも、訴訟物は同じとなる。
(3)例えば、従業員が会社の業務で怪我をした場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権(債務不履行責任)と不法行為に基づく損害賠償請求権の二つの実体法上の請求権が両立(競合)する。
旧訴訟物理論では、原告がそのうち一つをだけを請求していれば、その権利のみが訴訟物となる。(旧訴訟物理論であっても、原告は、債務不履行責任が認められなければ、不法行為責任の有無を審理してほしい(選択的併合)、と主張すれば、両請求を訴訟物とすることもできる。)
これに対して、新訴訟物理論では、原告がそのうち一つをだけ主張していなくても、両請求権が一つの訴訟物となる。
(4)例えば、AとBの交通事故によって不法行為に基づく損害賠償請求権しか成立し得ない場合には、新訴訟物理論でも旧訴訟物理論でも、訴訟物は損害賠償請求権となり結果は同じである。
実体法説
(1)実体法説では、請求権競合の事案において、実体法の運用もしくは解釈として、どれか一つの請求権して整理する考え方をである。
(2)実際の訴訟の運営では、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権(債務不履行責任)と不法行為に基づく損害賠償請求権の二つの請求根拠が考えられるとしても、原告は有利な方を選択する。また、裁判は社会的に妥当な解決を導く仕組みです。例えば、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権(債務不履行責任)でも、不法行為に基づく損害賠償請求権でも、休業損害の計算方法も慰謝料の計算方法と同じであり、審理の方法も結果もほとんど変わりません。
裁判例の蓄積結果を踏まえて、実体上、整理してしまおう、という考え方も理解できる。
(3)確かに、運用レベルでは、競合する請求が整理、統一されていくのは事実です。例えば、休業損害の計算方法も慰謝料の計算方法と同じものを使っています。しかし、実体法のレベルで、請求権競合の場合の請求を統一する作業(議論)が進んでおらず、実体法説で訴訟物を議論するのは難しいところがある。
参考
小林秀之「新法学ライブラリ 10 民事訴訟法 第2版」269頁
旧訴訟物理論と新訴訟物理論の議論
1 議論する前提
旧訴訟物理論と新訴訟物理論のどちらが妥当かを議論する前提としては、①請求権競合の事案について、②給付の訴え、もしくは、形成の訴え(確認の訴え以外)であること、③訴訟物論によって結論が変わる問題であることが必要である。
2 請求権の競合
請求権競合の事案である必要性は前述したとおりである。
3 給付の訴えもしくは、形成の訴えであること
(1)確認の訴えの訴訟物は、原告の求める特定の権利、法律関係である。新訴訟物理論であっても、原告が、「◯◯の権利、法律関係を確認を求める。」と求めているのに、「◯の権利を求めているが、△の権利も競合(成立)も審判対象になる。」と考えることはできないからである。
参考
名津井吉裕「事例で考える民事訴訟法 」22頁
(2)形成権は、「形成権の行使を認めるべき事業がある。」ことを根拠に、一定の法律効果を発生させる。
形成の訴えでは、形成権の行使を求める事情ごとに請求権が併存することになる。例えば、民法770条の離婚原因は、それぞれの離婚原因ごとに、離婚請権が発生すると考える。
形成の訴えであっても、実体法で、その効果の発生原因が記載されている場合には、請求権競合の事案となる。
| 民法770条(裁判上の離婚) 1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
(3)なお、債務不存在の訴えは確認の訴えであるが、請求権競合の事案では、訴訟物論を議論する実益がある。旧訴訟物として、競合する請求を全て存在しないことの確認の訴えとして構成するか、新訴訟物理論を前提に、これらは一つの訴訟物であるとして構成するか、考える必要がある。もっとも、説明の違いに過ぎず結論に大きな影響は与えないでしょう。(名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法」14頁参照)
3 訴訟物論によって結論が変わる問題であること(4つの試金石)
(1)旧訴訟物理論と新訴訟物理論のどちらが妥当かを議論する前提としては、訴訟物論によって結論が変わる問題であることが必要です。
(2)かつては、以下の4つの問題で、訴訟物が議論されてきました(4つの試金石)。
①訴えの変更(143条)の要否
②請求の併合(136条)の可否
③二重起訴の禁止(142条)
④既判力の客観的範囲(114条1項)
(3)現在では、③と④と、⑤裁判所の釈明の範囲(法的観点指摘義務)が中心に議論がされています。
(4)①②はあくまで、必要な手続や、理論的説明に過ぎず、議論は下火になってきています。
①訴えの変更(143条)の要否と、②請求の併合(136条)の可否
訴えの変更
(1)訴訟物が変更になる場合には、訴えの変更(143条)が必要になります。
訴えの変更に当たれば、新たな訴えとして、訴え変更の申立書を送達する必要があります。
(2)請求権競合の事案について、新訴訟物理論によれば、別の請求権に変更しても訴訟物は同一であるから、訴えの変更を経ずに認められる余地が出てくる。
(3)旧訴訟物理論によえば、別の請求権に変更する以上は訴訟物は別になり、訴えの変更が必要になる。
請求の併合
(1)請求権競合の事案については、二つの請求権を行使する場合には、旧訴訟物理論によれば、(両立しうる請求について、他の請求権が認められことを解除条件とする)選択的併合となる。
(2)これに対して、新訴訟物理論では、これらは、もともと一つの訴訟物となるから、選択的併合を認めない立場もある。(新訴訟物理論を採用しても、選択的併合を認める立場もある。)
③④訴訟物の範囲
(1)旧訴訟物理論と新訴訟物理論で、二重起訴や、蒸し返し訴訟の問題として、訴訟物の範囲が問題となってきた。
(2)実務は旧訴訟物理論を採用しながら、新訴訟物理論の観点での分析を踏まえて、実質的に前訴訟の蒸し返しにとなる訴訟については、信義則を活用して妥当な解決を図っている。
(3)両説の言い分は以下のとおりである。
| 新訴訟物理論からの批判 | 旧訴訟物理論の再反論 |
| (1)旧訴訟物理論では、請求権競合の事案で、別の請求で再訴が可能となる。新訴訟物理論の方が一回的解決が可能である。 (2)どの範囲で、蒸し返しであると判断するか、不明である。蒸し返しにあたるかについて、新訴訟物理論(前訴において、実質的に同じ給付を求めているかで判断する。)で判断するのであれば、それは旧訴訟物理論ではない。 | (1)実質的に前訴訟の蒸し返しにとなる訴訟は、裁判所が実質的に判断して、信義則で対応する。 (2)新訴訟物理論の観点でも訴訟物が同一であると判断できない場合にも、信義則による遮断が必要となる。したがって、信義則による修正を深えることは、新訴訟物理論でも必要である。 |