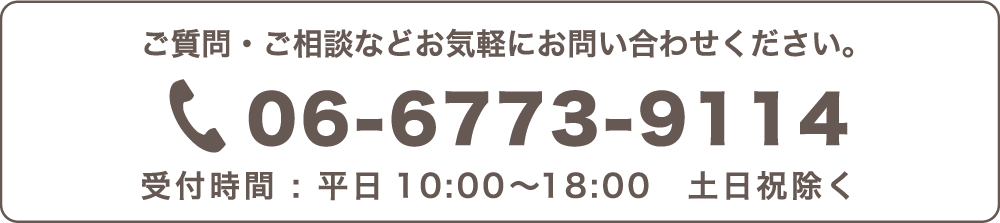【基本】訴訟物と実務2(旧訴訟物理論を前提とした実務)
2025/04/05 更新
訴訟物
(1)訴訟物とは、裁判における審判の対象のことです。
(2)旧訴訟物理論は、実体法の権利(請求権や、形成権)ごとに訴訟物を構成すると考える。
実務と旧訴訟物理論
(1)実務は、旧訴訟物理論を採用している。旧訴訟物理論を前提にすれば、原告の訴状の記載から訴訟物を特定し、原告の請求原因事実と、被告の抗弁を明確にすることができる。
これに対して、新訴訟物理論では、どこまで審判対象となっているか不明確であるからである。
(2)例えば、原告が以下の訴訟を書いたとする。なお、訴訟物は、訴状の「よって◯◯を請求する」(よって書き)等の訴状の記載を前提に判断される。
| 訴状 請求の趣旨 被告は、原告に対し100万円を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請求原因 1 消費貸借 (1)令和7年4月3日、原告は被告に対し、以下の条件100万円を貸し付ける合意をした。 返済日 令和7年7月末日 返済額 100万円 (2)令和7年4月3日、原告は被告に対し、100万円を銀行振込で送金する方法で支払った。 (3)令和7年7月末日は経過したが、被告は原告に返済しなかった。 2 貸付の動機 (1)もともと、被告は飲食店のオーナであった。 (2)令和7年3月ごろ、被告は原告に対し、2店舗目の飲食店をはじめる運転資金として貸してほしい、と説明していた。 (3)原告は、これを信じて、1のとおり、100万円を貸し付けた。 (4)令和7年8月ごろ、原告は被告と連絡が取れなかったことから、被告が運営していると聞いていた飲食店まで言ったところ既に閉店していた。隣のビルの1階の人に聞いたところ、令和7年3月末日には、被告は飲食店を撤退していた。 (5)同日まで、被告は原告を含めて、誰からも、令和7年3月末日には、被告は飲食店を撤退していたことを聞いたことはなかった。 (6)令和7年10月末日現在、2店舗目の飲食店についても、被告は開店準備をしていない。 3 被告の詐取 (1)以上を考慮すれば、被告は原告に対し、「2店舗目の飲食店をはじめる運転資金として使用する。」こと予定がないのに、これがあるかのように偽って、原告から100万円を詐取した。被告が原告からこれらを黙って貸金名目で100万円を交付させたことは刑法上の詐欺の要件に該当し、不法行為の故意過失に該当する。 (2)よって、原告は、被告に対し、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払いを請求する。 |
(3)本件の場合の訴訟物は、「令和7年4月3日、被告が原告を騙して100万円を交付させた不法行為に基づく損賠償請求権利」である。
(4)訴訟物が「不法行為に基づく損害賠償請求権」となることによって、原告の請求原因と、被告の抗弁が決まる。
原告の請求原因事実
①不法行為の故意、過失
②権利・利益の侵害
③損害
④因果関係
被告の抗弁
(1)例えば、被告が時効を検討するとき、原告が不法行為を選択したことで、起算点は貸付時(不法行為)となる。
仮に、原告が消費貸借に基づく返還請求権を選択していれば、起算点は、返済合意時となる。
(2) 例えば、被告が相殺の主張をけんとうするとき、原告が不法行為を選択したことで、被告はこの抗弁を提出できなくなる(509条)。
仮に、原告が消費貸借に基づく返還請求権を選択していれば、被告は相殺の抗弁を主張できたことになる。
弁論主義の第一テーゼ
(1)弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を裁判の基礎としてはならない」という原則である。
ここでいう事実は、当事者の主張した主張事実である。裁判所は、訴訟物を中心として、当事者が主張した主張事実についてのみ判断する義務があることになる。
(2)したがって、裁判所は、訴状物を中心とする当事者の主張をまって、この当否を判断する形で審理を進めることになる。