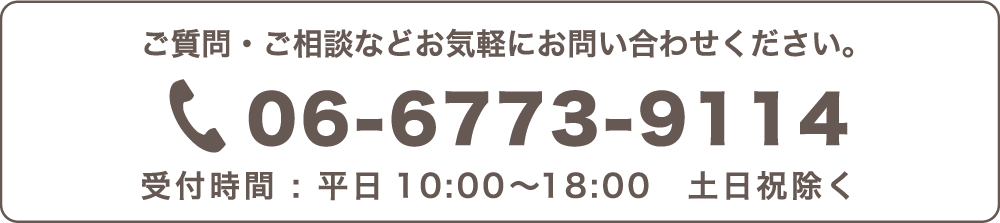【重要判例】判例(既判力の減縮)
2025/04/11 更新
最判平成9年3月14日判時1600号89頁
事案
(1)Aが死亡し、XとYは相続人である。
(2)Xは、Bから土地を購入したとして、Yに対し当該土地の単独所有権の確認と、所有権に基づく登記請求訴訟を提起した。
(3)Yは、亡AがBから土地を購入後に、Yに贈与したと主張した。
実体法上の整理
Yの主張が正しいとすれば、少なくとも、Xは亡きAの相続人として、当該土地の共有持分を有することになる。
訴訟の経緯
(1)Xは上記の主張をしなかった。
(2)裁判所は、亡AがBから土地を購入したが、Yに贈与したとは認定できないとした。
(3)裁判所は、Xに単独所有権が認められないとして、Xの請求を棄却し、同判決が確定した。
(4)その後、Xは亡きAの相続人として、当該土地の共有持分に基づいてYに対し共有持分の登記請求訴訟を提起した。
判決
(1)所有権確認請求訴訟において請求棄却の判決が確定したときは、原告が同訴訟の事実審口頭弁論終結の時点において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じるから、原告がその時点以前に生じた所有権の一部たる共有持分の取得原因事実を後の訴訟において主張することは、確定判決の既判力に抵触する。
(2)Xは、前訴において、本件土地につき売買および取得時効による所有権の取得のみを主張し、事実審口頭弁論終結時以前に生じていたAの死亡による相続の事実を主張しないまま、 Xの所有権確認請求を棄却する旨の前訴判決が確定したというのであるから、 Xが本訴において相続による共有持分の取得を主張することは、前訴判決の既判力に抵触し、許されない。
解説
1 単独所有権の確認の訴えは、共有持ち分の確認の訴えを含む
(1)判決は、前訴訟における、単独所有権を主張する所有権確認請求訴訟と、後訴訟における、共有持分に基づく当共有持分の登記請求権は所有権の一部であるとして訴訟物が一致します。したがって、前訴訟で、所有権一切が認められないことが確定していますので、後訴で、共有持分があると主張することは既判力に反するとしている。
(2)これについては、判決は、所有権確認訴訟においては、所有権所得原因ごとに訴訟物を構成するのではなく、所有権の存否について既判力が生じること、共有物は所有権の一部であるから、所有権確認請求の中に共有持分の確認を求める趣旨も含まれること、を前提にしている。
2 前訴訟での審理の問題
(1)前訴訟で、原告は単独所有権を主張していました。前訴訟の裁判所は、原告に共有持分があると認定することはできなかったのでしょうか。
(2)原告が、「Xは亡きAの相続人として当該土地の共有持分を取得した。」と主張していない以上は、上記の認定をすることは、弁論義務違反となります。
(3)しかし、裁判所は、「Xは亡きAの相続人として当該土地の共有持分を取得した。」と主張しないか、Xに釈明すべき義務があったのではないか、という疑問が生じます。
3 訴訟物が同じでも既判力が及ばない
(1)これを考慮すれば、裁判所の釈明義務違反がある以上は、前訴訟の既判力は例外的に及ばない、という結論も有り得たのではないか、と指摘されている(例外を認めるパターン)。
(2)これ対して、釈明義務が尽くされなくなった結果としてXの敗訴が確定した場合、釈明義務の対象となる事項については規範力が及ばず、後訴で審判対象になる、という考えもある(既判力を縮小させるパターン)
参考
越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法」 135頁
名津井吉裕 「事例で考える民事訴訟法」26頁以下
田中豊「論点精解民事訴訟法 要件事実で学ぶ基本原理」9頁以下
「民事訴訟法判例百選(第6版)」247頁以下
最判平成9年7月17日判時1614号72頁
事案
(1)Aが死亡し、Xは相続人である。
(2)Xは、自分が建物を建築したとして、Yに対し建物単独所有権の確認と、所有権に基づく登記請求訴訟を提起した。
(3)Yは、亡Aが建物を建築したと主張したが、Xはこれを争った。
実体法上の整理
Yの主張が正しいとすれば、少なくとも、Xは亡きAの相続人として、当該建物の共有持分を有することになる。
訴訟の経緯
(1)Xは上記の主張をしなかった。
(2)原判決は、Xに単独所有権が認められないとして、Xの請求を棄却し、Xが上告した。
判決
「原審の確定したところによれば、Bは昭和29年4月5日に死亡し、Bには妻C及びXを含む6人の子があったというのである。 したがって、原審の認定するとおり、本件土地を賃借し、本件建物を建築したのがBであるとすれば、本件土地の賃借権及び本件建物の所有権は Bの遺産であり、これを右7人が相続したことになる。 そして、Xの法定相続分は9分の1であるから、これと異なる遺産分割がされたなどの事実がない限り、Xは、本件建物の所有権及び本件土地の賃借権の各9分の1の持分を取得したことが明らかである。」
「Xが、本件建物の所有権及び本件土地の賃借権の各9分の1の持分を取得したことを前提として予備的に右持分の確認等を請求するのであれば、 Bが本件土地を賃借し、本件建物を建築したとの事実がその請求原因の一部となり、この事実についてはXが主張立証責任を負担する。 本件においては、Xがこの事実を主張せずかえってYらがこの事実を主張し、Xはこれを争ったのであるが、原審としては、Yらのこの主張に基づいて右事実を確定した以上は、Xがこれを自己の利益に援用しなかったとしても、適切に釈明権を行使するなどした上 でこの事実を斟酌し、Xの請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきものと解するのが相当である (最高裁昭和38年 (オ) 第1227号同41年 9月8日第一小法廷判決・民集20巻7号1314頁参照)。」
「原審がこのような措置を執ることなく前記のように判断したことには、審理不尽の違法があり、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 論旨は、右の趣旨をいうものとして理由がある。 したがって、原判決のうち別紙記載の部分は破棄を免れず、右部分につき、Yらの抗弁等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、右破棄部分以外の原判決は正当であるから、この点に関する上告を棄却することとする。」
解説
1 単独所有権の確認の訴えは、共有持ち分の確認の訴えを含む
(1)共有物は所有権の一部であるから、原告の所有権確認請求の中に共有持分の確認を求める趣旨も含まれる。に(2)前訴訟で、原告は単独所有権を主張していました。前訴訟の裁判所は、原告に共有持分があると認定することはできなかったのでしょうか。
(2)原告が、「Xは亡きAの相続人として当該土地の共有持分を取得した。」と主張していない以上は、上記の認定をすることは、弁論義務違反となります。
(3)しかし、裁判所は、「Xは亡きAの相続人として当該土地の共有持分を取得した。」と主張しないか、Xに釈明すべき義務があったのではないか、と釈明義務違反を認めました。
参考
名津井吉裕 「事例で考える民事訴訟法」26頁以下
田中豊「論点精解民事訴訟法 要件事実で学ぶ基本原理」9頁以下
「民事訴訟法判例百選(第6版)」98頁以下