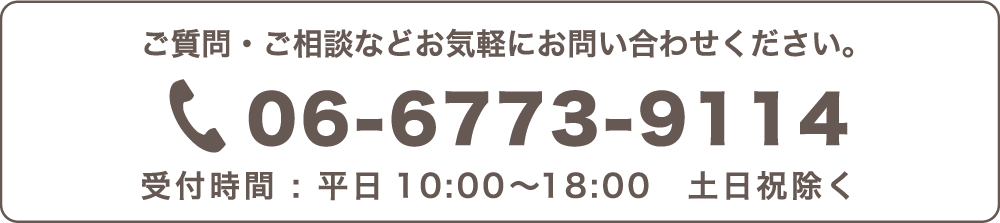【論点】当事者の確定
2025/04/03 更新
| Q 当事者の確定はどんなときに、問題となるのか。 A (1)訴状に記載された当事者(原告と被告)が、裁判所で当事者として活動するのが原則である。 (2)しかし、以下のようなに、訴状に記載された当事者(原告と被告)とは別の者が、裁判所で当事者として活動した場合、当事者の確定や、当事者の変更が必要となる。 (3)訴状の到達時に、訴状に記載されていた原告または被告が死亡していたときに、問題となる(死者名義訴訟)。 (4)訴状の到達時に、第訴状に記載されていた原告または被告の名前を騙って、第三者が裁判所で訴訟を活動をして、誰も気がつかないまま判決が確定したとき等に、問題となる(氏名冒用訴訟)。 参考 長谷部 由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」22頁 |
| Q 当事者の表示の訂正とは何か。 A 当事者の同一性があれば、表示の訂正の問題である(事件の内容や、住所の記載等から同一性を判断できる場合がある)。 氏名の誤記などがこれにあたる。 参考 遠藤賢治「事例演習民事訴訟法 第3版」25頁以下 |
| Q 当事者の確定が問題となる(当事者の基準を論述する)のはどんなときか。 A (1)訴状に記載された当事者(原告と被告)とは別の者が裁判所で当事者として活動した場合には、当事者の基準によっては、裁判所で当事者として活動した者等を当事者として妥当な結論が導くことが考えられる。したがって、当事者の確定が問題となる(当事者の基準を論述する)。 (2)例えば、訴状記載の被告Aが死亡し、唯一の相続人がBだとする。BがAを名乗って応訴したときには、応訴したという意味で行動説によれば、当事者はBでありBに判決の効力が及ぶ。 実体法で考えれば、被告Aが死亡すれば、その地位を相続人であるBが引き継ぐ。意思説によれば、被告人Aが死亡していたのであれば、被告は相続人(のB)であると考える。 参考 遠藤賢治「事例演習民事訴訟法 第3版」27頁以下 山本和彦ほか「Law Practice民事訴訟法〔第5版〕」 34頁以下 |
| コラム (1)訴状の到達時に、訴状に記載されていた原告または被告が死亡する(死者名義訴訟)事案については、裁判例は統一的な見解を採用していない、とも言われる。 (2)最判昭和41・7・14民集20巻6号1173頁は、訴状送達前に被告が死亡した場合において、 その相続人が第1審で訴訟承継の手続をとり、控訴審まで訴訟遂行しながら、上告審で訴状送達前の被告の死亡を主張することは、信義則上許されないとした。 この事案は意思説や行動説によると、当初から相続人が被告であったことになる。 (3)死者を被告とする訴訟において,、原告の意思を実 質的に解釈し、または相続人の行動等や,訴訟経済等を考慮して、 実質上の被告は相続人であると解し, 表示の訂正を認めるものが多い。 (3)これに対して、表示説の立場に立ち、表示の訂正は認められないとして、死者を被告とする訴えを却下するもの (東京高判昭和54・8・30判時943号 60頁) や,、表示説を採用 し、判決確定後に被告死亡の事実が判明した場合に, この判決の効力は相続人に及ばないとするもの (神戸地判 昭和29・5・7下民集5巻5号665頁) がある (4)裁判例の見解が統一的ではないが、これは具体的な事案解決の妥当性を目指した結果だとも言われている。 参考 高田裕成 ほか「民事訴訟法判例百選(第6版)14頁 |
| Q 当事者の基準にはどのような説があるのか。 A (1)基本的な考え方としては、①訴状に記載された当事者(原告、被告)が訴訟の当事者となる(表示説)、③原告の意思によって決まる(意思説)、裁判所で当事者として振る舞った者とする(行動説)がある。 (2)もっとも、意思説や、行動説では、どのような意思、どのような行動で当事者が決まるのか明確にならない。 (3)したがって、当事者とは、訴状に記載された当事者とする考え方(表示説)が通説である。 参考 名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」54頁以下 |
| コラム 表示説の中でも、訴訟の記載を当事者欄だけでなく、請求の趣旨、請求源を含めて客観的に合理的に解釈すべきる、とする実質的表示説もある。 なお、実質的表示説については、意思説と大差なくなるという批判もある。 参考 遠藤賢治「事例演習民事訴訟法 第3版」25頁以下 |
| Q 訴状の到達時に、訴状に記載されていた原告または被告が死亡した場合(死者名義訴訟)、訴訟手続としてどのような問題があるのか。 A (1)民事訴訟では、訴状が被告に送達されて訴訟事件が係属する。しかし、被告への訴状送達前に、訴状に記載されていた原告または被告が死亡した場合(死者名義訴訟)には、当事者を欠くことになって訴訟係属が生じない。 (2)この場合には、訴状の補正(137条)や、訴訟手続の受継(124条)もありえない。 (3)そこで、原告は、再度、本来の被告に対し訴状を送達し直す必要がある。 参考 山本和彦ほか「Law Practice民事訴訟法〔第5版〕」 31頁以下 |
| Q 訴状記載の当事者(原告、被告)とは別の者が、裁判所で当事者として活動したが、本来の当事者が、あえてその者の訴訟手続を引き継ぐことができる(任意的当事者変更)。しかし、その手続の法的性質については、どう考えるのか。 A (1)訴えの変更(143条)は当事者の変更を含まない。また、従来の当事者とは異なる者が訴訟を引き継ぐ訴訟係属(50条1項、51条)があるが、同制度は、このような場合を想定していない。 (2)したがって、この手続きは、新訴の提起と旧訴の取り下げが併存する複合行為である。 参考 遠藤賢治「事例演習民事訴訟法 第3版」25頁以下 |
| Q 訴状記載の当事者(原告、被告)とは別の者が、裁判所で当事者として活動して、判決が確定してしまった場合、本来の当事者は、新たに訴えを提起すべきか。再訴の訴えによるべきか。それとも、、あえてその者の訴訟手続を引き継ぐことができる(任意的当事者変更)。しかし、その手続の法的性質については、どう考えるのか。 |