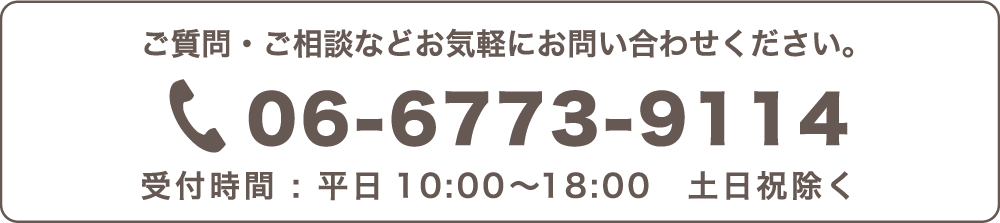【民事訴訟法から見た民法】錯誤
2025/04/21 更新
錯誤
(1)民法95条の錯誤とは、内心と表示が不一致であることです。
(2)民事訴訟では、当事者の意思を当事者の言動により認定します。
(3)つまり、錯誤とは、「ある行動からみれば、Bしたい。」と考えてるように思えるが、「ある行為からすればAしたい。」状態のときに成立します。
(4)例えば、契約当事者は、Aの土地を売却しようとAの土地を訪問して、土壌汚染がないかチェックしたりしていた。しかし、契約書は「土地Bを売る。」と記載されていた場合には、これにあたります。
二段の推定
処分証書とは、意思表示などの法律行為を記載した文書であり、民事訴訟においてその成立の真正が認められれば、記載された内容が正しいと推定されます。例えば、契約書や遺言書などが
「契約をする。」との意思と、これを伝える「Aの言動」(表示)を区別します。しかし、その当事者の意思は、当事者の言動から推察することになります。
したがって、民事訴訟法で「Aの言動」と、その言動からその人の意思がどのようなものだと理解できるのか、が問題となります。
契約行為
(1)例えば、以下のAの言動であれば「Aが〇を購入したい。」という売買契約の申込みと評価されます。これに対して、Bの言動が「Aの申込を承諾した。」評価されれば、契約が成立します。
① 例えば、Aが「車を100万円で購入する。」と書かれた契約書ににサインする行為
② 例えば、Aがインターネットでクレジット情報を入力し、「購入する」と書かれたボタンをクリックする行為。
③ 例えば、Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。
例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)。
(2)民事訴訟においては、合意の有無が争点となれば、当時の当事者の言動の有無、内容が争点となります。
黙字の意思表示
(1)黙示の意思表示とは、口に出したり文章で伝えはいないが、特定の行為意思を示すものと理解される、行動をいいます。
(2)例えば、「Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。」
は、「売買契約を締結する。」という明示の表示をしていませんが、「100円で缶コーヒーを購入するしたい。」 という意思を読み取ることができます。
(3)「例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)。」も、同じく、「100円で缶コーヒーを売買する。」 という意思を読み取ることができます。
(4)これらは、「売買契約を締結する。」という黙字の意思表示です。