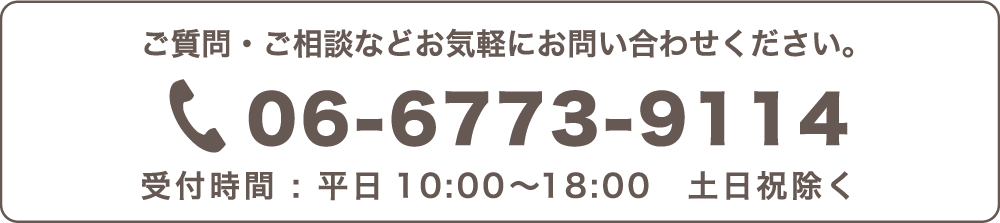【上司の心得】YES&BUT法
2023/02/03
YES&BUT法
(1)YES&BUT法は、相手の言い分を肯定してから、別の意見をいう方法です。
(2)感情的な対立を防ぐ方法として注目されています。
YES&BUT法(例1)
上司
「山田さん(部下)は、A案と思ったのですね。」
「こここの点は●●ですばらしい。」
「この意見は△を意図したということですよね。」
「ところで、△を意図するなら、B案はどうでしょうか。」
という形で、会話を進めます。
YES&BUT法(例2)
上司
「私は、●●さん(部下)に、『取引先に書類を出してほしい。』と頼みました。」「私としては、会議資料なので、会議前に取引先に渡しておいてほしかったのです。」「しかし、●●さん(部下)は、これを会議当日に持って行くという対応をされました。」「同じようなミスをしないために、どんなルール(手順)があればよいのか、一緒に考えましょう。」「どんなルールがあれば、ミスが起こらなかったでしょうか。」
部下
申し訳ありません。すべて私の責任です。
以後、反省します。
上司
責任の所在を確認したいのではありません。
例えば、仮に、〇〇さん(部下)が100%悪いとしても、会社としては同じミスを出すわけにはいかないのです。
同じミスをしないために、私の方でできること、周りの方でできること、もちろん、〇〇さん(部下)できることを確認し、それをルール化させたいと思っています。
部下
そうおっしゃるのであれば、「『事前』に送るとメモ等に記載して渡してほしかった。」です。
上司
メモ等に書くという一つの解決策かもしれません。しかし、私もややこしい指示を出すときには、メールで送る等の工夫をしています。
「〇〇さん(部下)が私の立場に立って考えてもらますか。」「書類をチェックして、〇〇(部下)さんに返して、そのときに『書類を送ってほしい。』と返事しました。」「そのときに、付箋で、『今すぐメールで送ってほしい。』というレベルでメモを付けるとすると、メモだらけになりませんか。」「そのような取り扱いをした場合に、かえって分かりにくくなると思いませんか。」
部下
それはそうですが。
上司
「会議資料は事前に検討してもらう必要があります。したがって、会議資料は事前に送る必要があるということを意識してもらう。」ということだと思います。
部下
分かりました。以後、気をつけたいと思います。
YES&BUT法(例3)
部下
「A案です。」
上司
上司は、本音では、「A案はダメだ」と思っている。
「難しいですね。この点を詳しいBさんに聞いてみますね。」
Bさん
Bさんが説明する。
上司
「なるほど、Bさんの見解の利点も分かりました。」「私も詳しくなくて勉強になりました。」
解説
(1)上司が自分も分からないという形で、部下へのショックを和らげています。
(2)意見を否定する際に、「発言者の発言を褒める。」もしくは「その問題は難しいので、間違えても当たり前。」という形を作ります。
確証バイアス
(1)確証バイアスとは、自分の考えを正しいと思い込んでしまい、これに反する情報を遮断し、自分にとって都合のよい情報だけを取得してしまう心理的な傾向です。
(2)YES&BUT法を使うことで、確証バイアスの弊害を和らげる効果もあります。
部下の「自分の話を聞いてもらっていない。」という不満
(1)最近は、学校教育で「YES&BUT法」が取り入られています。部下からすれば、社会にでて、いきなり意見を否定される経験をするのです。
(2)部下は、「〇〇さん(上司)は、人の話が聞けない人である」と感じることがあります。また、確証バイアスにより、部下が上司の話を聞くのを妨げて、「〇〇さん(上司)は、わけの分からないことをいう人である。」と感じることがあります。
上司が「YES&BUT法」を使うべきか。
(1)「YES&BUT法」を使うと、コミュニケーションにかかるコストが増えます。新人指導では、新人の考えを一つ一つ訂正する必要があり、実際にこれを導入すると、上司の時間を圧迫します。
(2)上司が「YES&BUT法」を使うよりも、新人が相談するメンターを設けて、その人に使ってもらうのがよいでしょう。
(3)なお、上司が新人社員に、「きつい言い方しかできなくてごめん。私の悪いところです。」と適度に謝るのもよいでしょう。
次の記事 »
専門家である医師に意見を聞きに行く方法