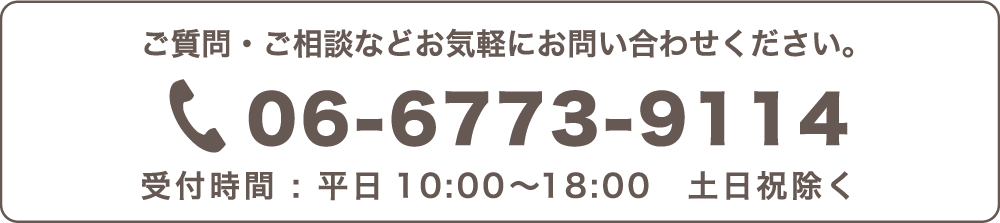PLG(プロダクト主導ビジネス)と料金の設計
2022/12/20
製品の価値
製品の価値は、以下の3つです。
1 機能的価値
その製品の機能及びこれによって得られる価値である。
2 感情的価値
毎月行っていた10時間の単純作業が1時間で終わったときの、イライラが無くなったときの心理的な価値である。
3 社会的価値
ある仕事を上手くできるようになることで、上司に褒められる等の価値である。
価値の指数
(1)ある製品の価値が増えれば、増えるであろうアプトプットを価値の指標と呼ぶ。
(2)例えば、動画編集ソフトがあるとして、その動画編集ソフトで作られる動画の本数が増えることは、動画ソフトの価値が増えたことの測定に使えるだろう。
(3)その指数の高いユーザーをヘビーユーザーと呼ぶ。
ユーザーの分析
(1)ヘビーユーザー、解約ユーザーに分けて分析する。
(2)ヘビーユーザーの属性(性別、職業、住所、能力)を確認する。
この点はヘビーユーザーに、直接、ヒアリングしてもよいだろう。
(3)ヘビーユーザーが使っている機能を確認しよう。
(4)解約ユーザーに、直接ヒアリングして、解約理由を聞こう。
ヘビーユーザーへの質問
(1)いくら以上だと、高すぎて、製品を購入しないか。
(2)いくらだと、製品をお得だと考えるか。
(3)別の製品を使うとすれば、どの製品を使うか。その製品を購入する理由は機能なのか。価格なのか。
PLG(プロダクト主導ビジネス)
(1)PLGは、Product Led Growt(プロダクトレッドグロース)という。
(2)一定の量・一定の機能について無料で使えるようにしておき、これを超えた機能・量を利用したいと考える際に、初めて料金を取る販売戦略です。
(3)有料プランにアップグレードする必要がないような無料プランを作ってしまうと、アップグレードされません。逆に、ユーザーにとって価値があると思う機能を無料にしなければユーザーを獲得できません。バランスをとった設計が必要です
有料で使える機能と、無料で使える機能
(1)A機能を有料化する(A機能を使えないとする)とヘビーユーザーをどれだけ失うのか。この数が多いとすれば、無料で使える機能にする。
(2)機能を無料とすることで、お金を支払うヘビーユーザーがどれだけ減るのか。これが多いとすれば、有料で使える機能にする。
(3)各機能を数値化して、無料で使える機能を決めていくことになります。
参考
ウェス・ブッシュ「PLG プロダクト・レッド・グロース「セールスがプロダクトを売る時代」から「プロダクトでプロダクトを売る時代」へ」108頁~167頁