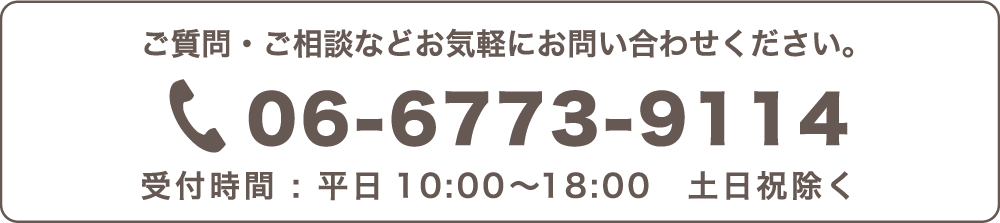ゲーミフィケーション
2021/09/18
ゲーミフィケーション
ゲーミフィケーションは、人が意欲的に取り組めるように、ゲームの要素を他の分野(教育や仕事)に取り入れる試みです。
①タスク・課題が明確であること。
例えば、マリオの課題は右に行くことだけです。
お願いする仕事も細かく分割できないか、考えてみましょう。HPの記事の作成を依頼するのであれば、テーマの決定と、記事の作成で二つに分けることが考えられます。
②「推理する。」「考える。」ことが必要があること。
ゲームでも謎解きは、王道です。
難しいのは、①と②が矛盾することです。(ゲームバランス)
仕事についても課題をだけ与えて解決策を自分で考えさせる仕組みが大切です。
案件を担当者として任せてその処理を任せます。その仕事を分割して、一つ一つ遂行について報告、連絡、相談させる等が考えられます。
③自分で選ぶこと。命令されないこと。
ゲームだって、ゲームすることを命じれられたら面白くありません。
仕事に拒否権を与えてはどうでしょうか。
他人に無理やり仕事をさせることはできません。
マネジャーの仕事を、メンバーの進捗を確認することと、不都合があれば、その分量や、担当の変更等の調整することです。
なぜ、メンバーがやらないのか悩んだり、感情的になったりしてはいけません。
メンバーを信頼し、何度も何度もチャンスを与えるのが仕事です。
メンバーに拒否権を与えてみる。
拒否権が発動されたら、仕事の分量の調整や、担当者の変更等を行えばよいのです。
④「挑戦できること」「環境が変化すること」
ゲームでは、新しいステージ、新しい敵が現れます。
仕事でも、会社全体として新しい分野に挑戦し、メンバーに新しい仕事を与えなければなりません。
⑤アフォーダンス
デザインによって、どのように操作すればよいのか直感で伝える仕組みをアフォーダンスといいます。
例えば、マリオは右を向いており、右に向かうことがゲームの目的であることを示しています。
アプリ等でも直感的なUIが大切にされています。
⑥ストーリー
例えば、マリオでは、さらわれたピーチ姫を救うのがミッションです。
仕事では、ミッションがこれにあたります。やっぱり、自分の仕事が「社会を変える」「お客さん(人)を救う」等のマクロ的、ミクロ的な的なストーリーが大切です。
お客さんとの面談に、事務員を同席させるとモチベ―ションがあがります。
裁判の傍聴や、(どういう事件なの知ってもらうために)記録の読み込みしてもらったりしています。
⑦仕事に対する反応、進捗状況の可視化
マリオはゴールすると、花火があがります。コースをクリアーすれば、新しいコースが出現出現してきます。
仕事を分割すれば、それだけでも一つ一つ達成感がでてきます。
プロジェクトの達成状況をガントチャート等を使って見える化することは大事です。
営業成績を貼り出すのもこのためです。
仕事をやってくれた従業員へのお礼も大事です。少なくとも1日1回は、従業員にお礼を言いましょう。
塾で成績を貼り出したり、資格取得の証明書を発行するなどがあたります。
最後に
ワーカーホリック、趣味は仕事、そういう人はたくさんいます。
仕事が楽しくない原因は、業績不振、人間関係です。これは経営者が介入して解決すべき問題です。
「仕事 楽しくない 理由」等でネット検索してみましょう。リストがでてきます。思い当たるものがあれば、一つ一つ解決していきましょう。
次の記事 »
労働保険事務組合