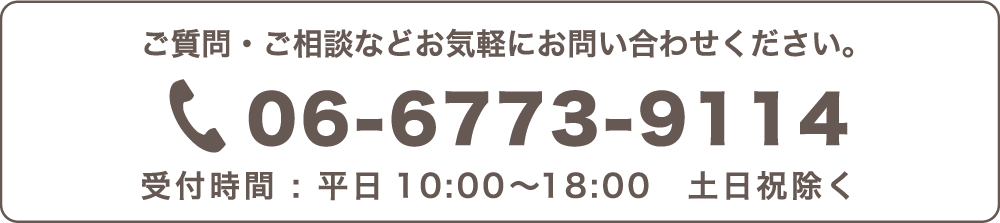【データと人事】人事データと活用のポイント
2024/01/10 更新
マイクロソフトの働き方データ
(1)マイクロソフトは、働き方をデータ化し、見える化しています。
(2)例えば、以下の事実がデータで分かったとのことです。
〇 部下の数が5人以下と、6人以上で上司の負担は大きく変わる。
部下の数は5人以内が望ましい。
〇 部下からの信頼が厚い上司はメールの返信が3時間早い。
これは、部下の質問等に、上司が素早く対応していることを意味します。
〇 結果を残すのは個人で力を発揮する人ではなくコラボできる人である。
〇 優秀な人ほど「誰にも邪魔されない集中タイム」を多く持っている。
〇 人数の多い会議は生産性もやる気も下げる。
〇 ハイパフォマーほど「自分仕切り」の会議が多い。
参考
沢渡 あまね「職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」 」
データの活用のポイント
(1)データを分析して、直感と大きく違った結果を出すことはできません。
(2)データ収集でできることは理解しておくこと必要があります。
データの活用でできること
(1)データ化することで、経験則で行っていた戦略を、誰にでもできるようにすることができます。
(2)データ化することで、現場の肌感を数値化してメンバーで共有して議論することができます。
(3)データの収集を自動化して、これを一覧できるダッシュボードを作れば、現状のリアルタイム把握が可能になります。