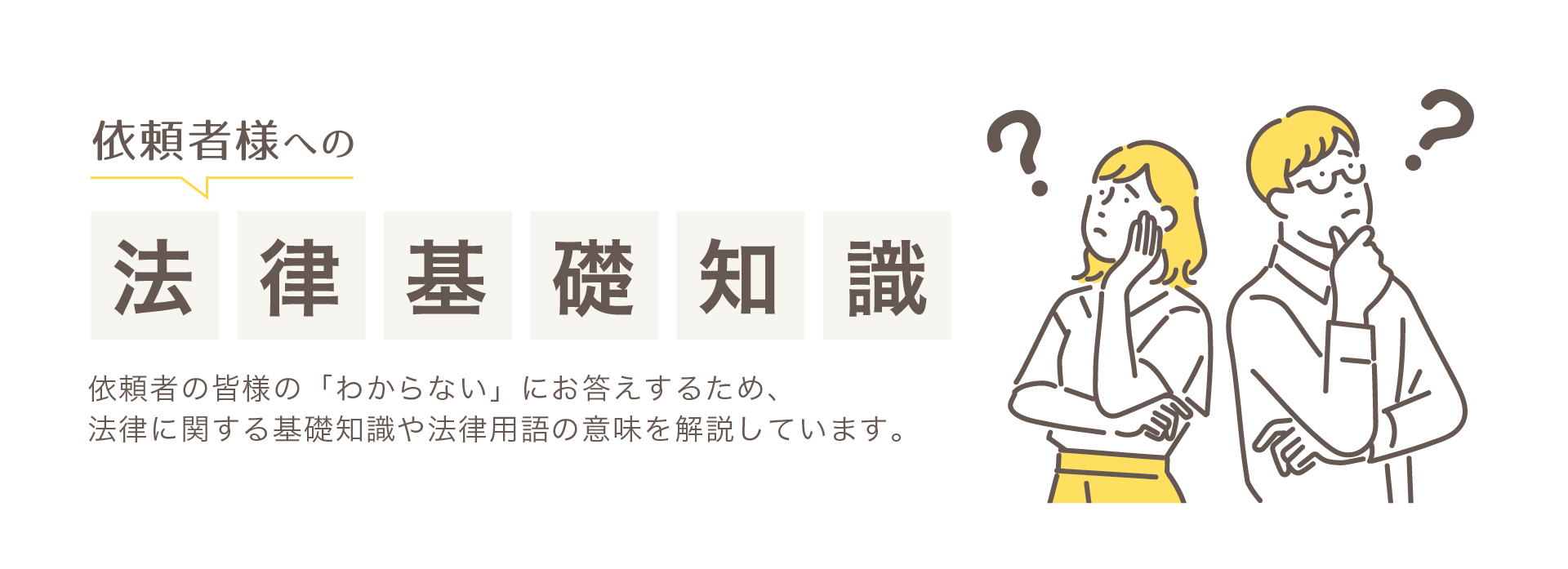判例(ある個人に対して誹謗する投稿について、その個人について知識・面識がある人でなければ誰のことが分からない場合でも、その個人について知識・面識がある人物がおり、その人がその誹謗中傷の投稿を拡散等するおそれが有る場合には、名誉棄損が成立する。)
2026/01/04 更新
このページを印刷誹謗中傷する投稿について、その個人について知識・面識がある人でなければ誰のことが分からない場合
1 一般的基準説
事実の摘示が社会的評価を低下させるかは、一般人の通常の注意力を前提に、その人の社会的評価が低下するかを基準とされます。
2 同定可能性
(1)一般の読者からみて、その投稿にて誹謗中傷されている個人が不明である場合には、その人の社会的信用性が損なわれることはない。
(2)しかし、その個人について知識・面識がある人が、誰に対する誹謗中傷されているのか理解でき、その人が誰なのか不特定多数に伝える可能性がある場合には、名誉毀損が成立する。これを同定可能性といます。
3 伝播可能性
(1)そもそも、名誉棄損が成立するためには、その名誉毀損行為を不特定多数が目にすることで、その人の社会的信用性が低下します。これを伝播可能性といいます。
(2)同定可能性と伝播可能性は別の概念です。もっとも、ともに不特定多数への伝播可能性を問題とする点で類似します。
東京地判令和6年7月18日
(1)被告はフェイスブックで、「Fの所属していた道場の道場主が、Eに対し後遺症が残るほどの大怪我を負わせた。」と記載したが、後遺症が残るほどという部分は虚偽でありました。
(2)Fの所属していた道場の道場主が誰であるかは、Fの知人にしか分かりません。しかし、被告のフェイスブックには、多数のフォロワーがおり、その者の中には、Fの所属していた道場の道場主が誰であるかは判断できる者もおり、その者らがその投稿を自分の知人等に共有する(フェイスブックの)シェア機能を使って拡散させる可能性があったことから、名誉毀損が成立すると判断されました。
判例タイムズ1534号237頁