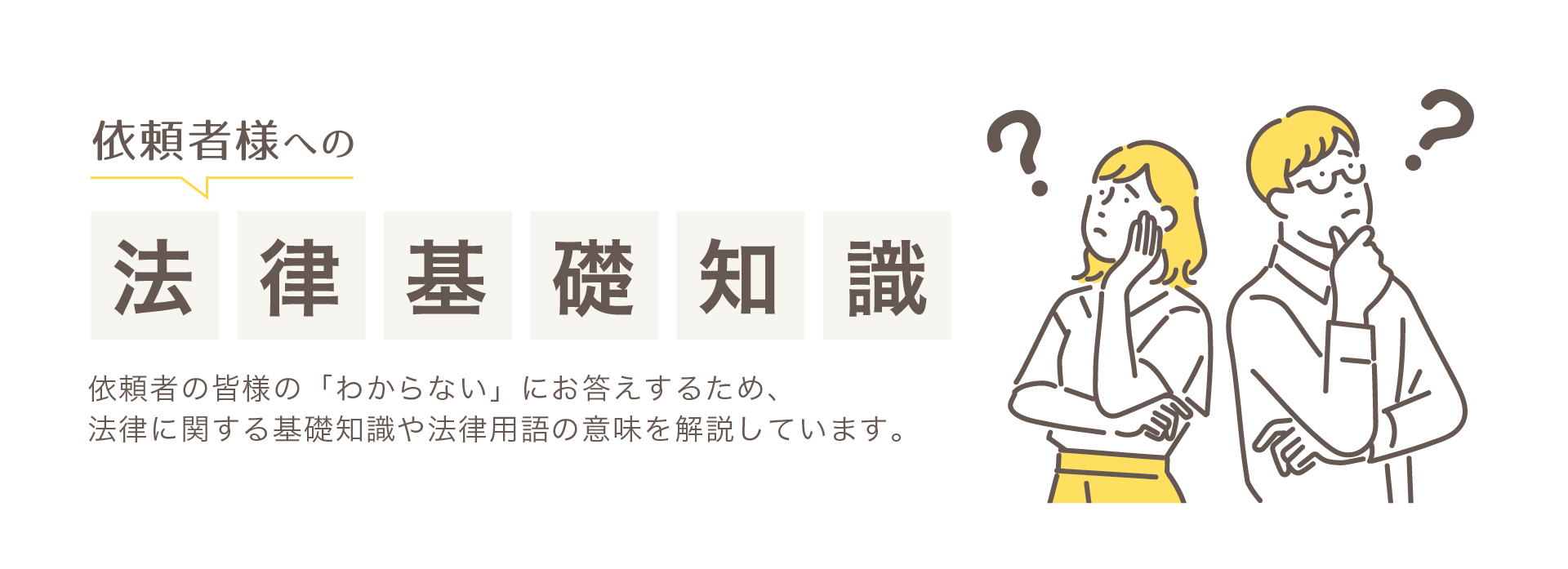一般危急時遺言
2025/03/27 更新
このページを印刷一般危急時遺言
(1)一般危急時遺言は、①死亡の危急に迫った者(死の危険が迫っている者)は、証人3人以上が立ち会うことを条件に、自分で遺言書を書かなくても、口頭でその内容を説明することで遺言を書いてもらうことができます。
(2)一般危急時遺言は、遺言の内容を聞き取った者は、 遺言書を代書して、記載した遺言の内容を遺言者と他の証人に読んで聞かせて、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 これに署名し印を押す方法で作成します(民9767条1項)。
(3)一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません (民976条4項)。
(4)一般危急時遺言については、具体的なやり取りが遺言を作成する意図でのやりとりだといえるか、もしくは、遺言能力が問題となります。
一般危急時遺言を利用する場合
(1)一般危急時遺言は、入院中の遺言者が容態が急変した場合や急な手術前に、公証人を呼ぶ時間の余裕がなく、かつ、自分で遺言を書けない場合に利用します。
(2)一般危急時遺言を後に清書してから署名押印するなどの場合があります。 遺言者の話を証人の1人がメモし、これを自宅に持ち帰って清書して署名押印し、他の2人の証人も署名したが印鑑を持参しなかったので署名をしないまま再び病室で清書した内容を遺言者に読み聞かせ、遺言者が確認したの でそのまま持ち帰り、翌日遺言執行者に指定された弁護士の事務所で2人が 押印したという事例で、一般危急時遺言の効力を認めた判例があります (最判昭和47・3・17民集26巻2号249頁)。
遺言確認審判と遺言無効確認訴訟
1 遺言確認審判
(1)一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じない (民法976条4項)。
(2)家庭裁判所は危急時遺言が遺言者の真意に出たも のであるとの心証を得なければこれを確認することができないとされている (民法976条5項)。もっとも、遺言者の真意については、一応真意ら しいという程度の緩和された心証で足りるとする。
2 遺言無効確認訴訟
(1)前述したように、遺言確認審判では、遺言者の真意については、一応真意ら しいという程度の緩和された心証で足りるとする。したがって、遺言確認審判が存在しても、遺言無効確認訴訟において、その遺言が有効であると判断されるわけではない。
(1)一般危急遺言を争う者は、遺言確認審判がなされていたとしても、別に、遺言無効確認訴訟を提起することができます。
参考
判例タイムズ1529号130頁