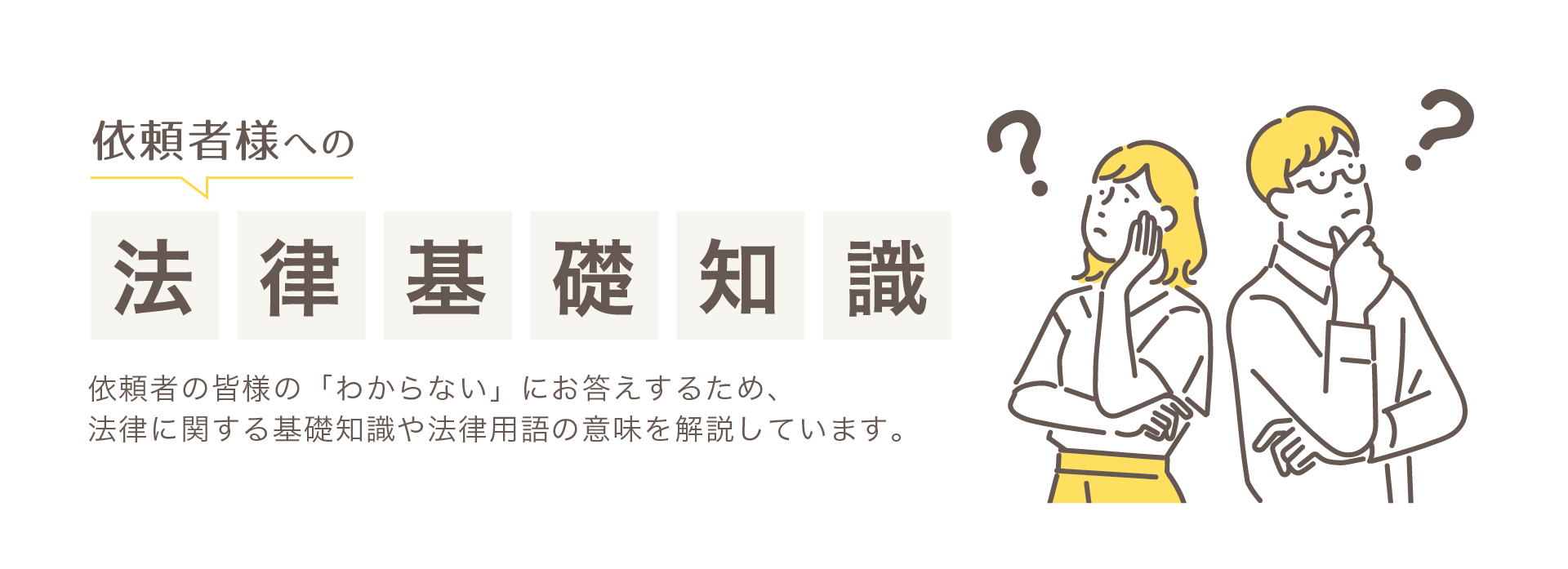判例(被告の訴訟活動が不適切であり、不法行為としての「違法」になるには、著しく相当性を欠く場合に限られる。)
2025/06/29 更新
このページを印刷東京高判令和6年1月31日
- 事案
- 過去の事件で、元従業員が会社を訴えた。その民事事件は終了した。
元従業員が、会社に対して、上記の民事訴訟において会社側が虚偽の主張や陳述を行った。
被告(会社)の訴訟手続における対応が、著しく相当性を欠くとして、その対応が不法行為としての「違法」にあたると主張し、損害賠償を請求した。
- 判決
- 裁判所は、応訴した者の訴訟活動が不法行為にあたる場合は、相手方を困惑させたり、訴訟による紛争解決を徒に遅延させたりするなどの不当な目的をもって、およそ裁判所に認められる余地のない事実の主張や立証のための訴訟活動をあえてするような場合に限られると判断しました。
そのうえで、会社側には、著しく不相当な訴訟活動にはあたらない、と判断しました。
(東京高判令和6年1月31日)
参考
判例タイムズ1529号149頁
解説
1 訴えの提起とその違法
原告の請求が正当かどうかは、訴訟提起後に、裁判所が判断することです。原告の請求が認められなかったからといって、原告の請求を全て違法だということはできません。
したがって、「原告の訴訟提起そのものが違法である。したがって、訴訟提起したことが不法行為の違法であるとして損害賠償義務を負う」と認定される場合は、訴訟提起そのものが著しく相当性を欠く場合に限られます。
補足
この点について、最高裁判例 (最三小判 昭63.1.26民集42巻1号1頁) は、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。」と判断しています。
その後の判例も同じです (最二小判平21.10.23裁判集民232号127頁、判夕1313号115頁, 最二小判平22.7.9裁判集民234号 207頁,、判夕 1332号47頁)。
2 被告の応訴とその違法
本件は、原告側の訴訟の提起ではなく、被告側の応訴が違法になるか問題となりました。
しかし、被告の訴訟活動の結果、その主張立証内容が裁判所に受け入れられなかったことから、 後日、 そのような主張立証を行ったこと自体につき不法行為責任を問われることとなれば、訴訟活動が萎縮し、裁判を受ける権利を不当に制約することになります。
特に、被告の場合には、訴えを提起されて対応をしなければ直ちに敗訴することや、争いつつも妥当な解決を図るという被告側での訴訟活動も否定されるものではありません。
したがって、被告の応訴活動が違法となるのは、原告の請求が違法となるのと同等もしくは、それ以上に「不適切」であることが必要です。
つまり、被告の訴訟活動が不適切であり、不法行為としての「違法」になるには、著しく相当性を欠く場合に限られます。
本判決では、応訴した者の訴訟活動が不法行為にあたる場合は、相手方を困惑させたり、訴訟による紛争解決を徒に遅延させたりするなどの不当な目的をもって、およそ裁判所に認められる余地のない事実の主張や立証のための訴訟活動をあえてするような場合に限られると判断しました。
本件では、会社側の訴訟活動がそのような場合に該当しないとして、元従業員の請求は棄却されました。