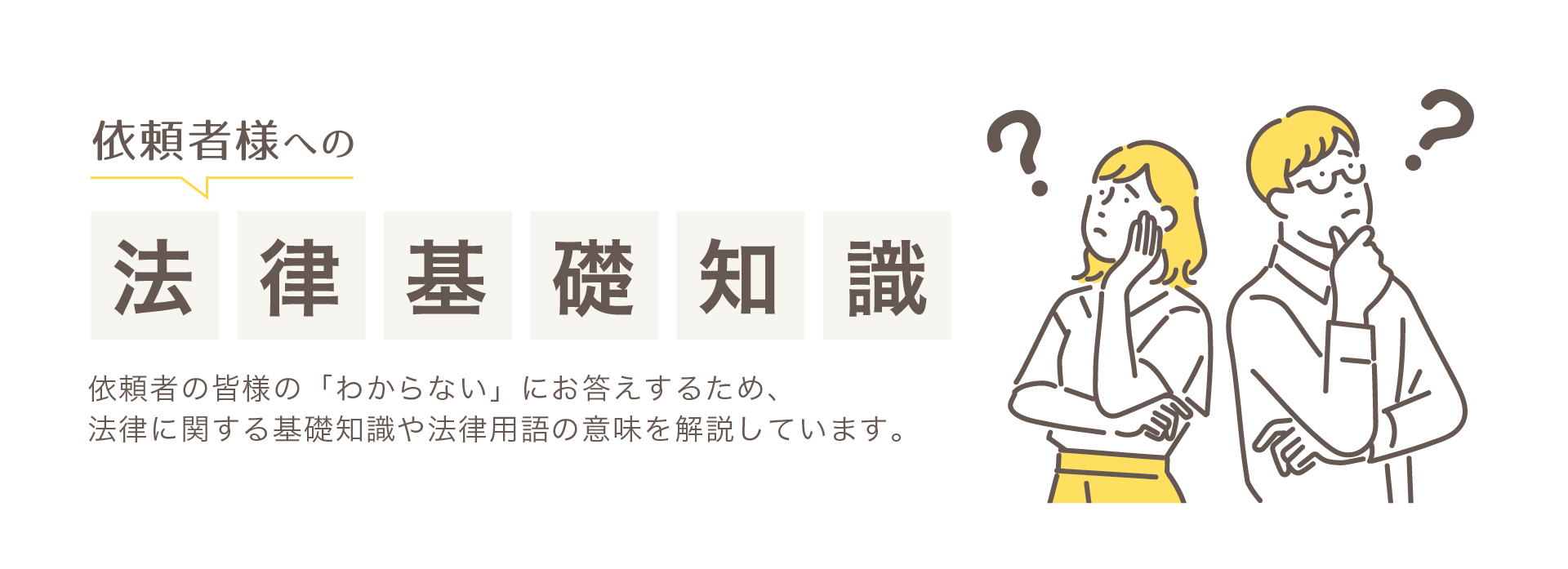控訴審と、和解についての意向確認
2025/04/23 更新
このページを印刷控訴審の流れ

控訴審では、新たな取り調べを行うことがほとんどないため、和解の検討に時間が割かれることが多いです。
控訴審は、第一審での審理の結果を引き継ぎます。したがって、新たな取り調べを行うことはほとんどありません。
控訴すると、第一審の判決の効力が消えて、判決を出す前の段階に戻るイメージです。控訴審の裁判官がもう一度判決を書くイメージです。
控訴審では、控訴人と被控訴人がお互いに書類を出し、第一回目の期日では取り調べ手続等は終了となり、第2回目の期日では判決が言い渡されることがほとんどです。
控訴審では、取り調べ手続等はすぐに終わり、裁判官主導で「和解できないか。」と和解の検討に時間が割かれます。
和解できないとなれば、第2回目の期日で判決となります。
控訴審と、和解についての意向確認
控訴状を提出すると、裁判所から、今後の進行について質問する文書が届きます。
その文書には、第一審での和解交渉の経過や、「控訴審での和解を希望するか」を記載して裁判所に回答することになっています。
控訴審の裁判官は、上記の書類での回答を参考に、「和解できないか」について双方に話をしていくことになります。
弁護士としての注意義務
控訴審において、弁護士は、裁判所に和解を希望しないと文書で回答するときには、依頼者に対し「和解を希望しない。」ことを確認する義務があります。(令和5年5月25日大阪高裁)
参考
判例タイムズ1520号43頁
和解は当事者双方が和解に同意しなければ成立しません。第一審で、一方当事者が和解を拒否している場合、控訴審で和解が成立する可能性は高くはありません。
したがって、上記の事件の弁護士が「和解できない。」と判断して、依頼者に確認することなく、裁判所に和解を希望しないと文書で回答した気持ちは分からなくはありません。
しかし、依頼者の意向を尊重すべき弁護士としては、意思確認をしっかりとすべきとされた判例です。