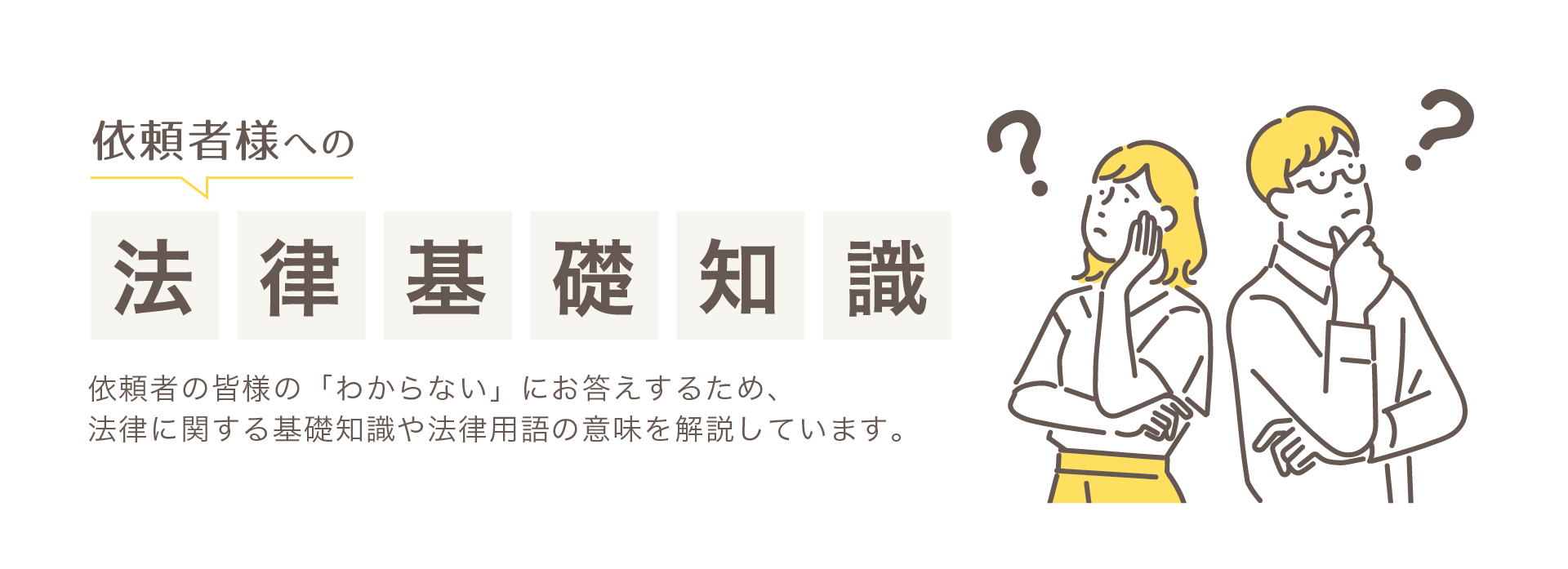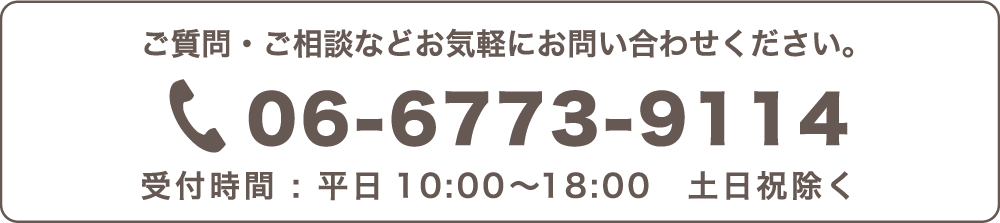【ステップ2】クレーマー対応の基本を確認する。
2023/10/17 更新
このページを印刷クレーマー対応の基本
(1)クレーマー対応の基本は、以下のとおりです。
(2)特に、お客様対応と、クレーマー対応では、基本方針が変わってきます。
1 感情的にならない
こちらが感情的に対応すれば問題は大きくなります。相手がどんなに理不尽を要求しても、感情的な対応は絶対にしてはなりません。
2 特別扱いはしない。理不尽な要求は飲まない。
(1)お客様であれば、事情を聞いて、特別な配慮をすることもあるでしょう。
(2)しかし、クレーマーの場合には特別扱いは厳禁です。特別扱いを認めれば、騒げば何かもらえると学習指定します。そうなると、要求がエスカレートし解決が難しくなります。
(3)クレーマーは、いろいろな方とトラブルを起こしています。クレーマーにとって一番、腹が立つ人物にならなければ、攻撃の対象は別のところにいきます。言うべきことは言っても大丈夫です。
(4)理不尽かどうか判断がつかないまま、要求がエスカレートしてくることがあります。2度ほど注意し、それでも関係を修復できない場合には、契約解除を前提とした対応をしましょう。
3 親身にならない。対応時間を決めてコントロールする。
(1)お客様であれば、親身なって話を聞くことは大切です。
(2)しかし、クレーマーは、どうにか自分の要求を通そうと必死です。クレーマーは、どうにか自分の要求を通そうために、協力的な相手方との関係に固執します。
(3)クレーマーは、いろいろな方とトラブルを起こしています。クレーマーにとって一番、腹が立つ人物にならなければ、攻撃の対象は別のところにいきます。事務的な対応に切り替えることが大切です。
(4)毎回の対応時間は、1回目が2時間なら、2回目は1時間、3回目は30分と減らしていくなど、対応時間を決めていきましょう。(なお、時間を減らすのは、関係を終わらせることが前提の戦略です。)
4 説得しようとしない。
(1)お客様が「分からない。」と困っていれば、十分な説明が必要です。
(2)しかし、クレーマーは、 自分にとって都合の悪い話は認めません。説得しようとすれば、お互いに感情的になります。
(3)クレーマーの説明は、手短に、同じ説明を繰り返しましょう。事務的な対応を行うことで、要求に応じられないことをしっかりとアピールするべきです。
5 文書で回答する。
(1)クレーマーの要求については、文書で回答を用意しましょう。
文書は第三者にチェックしてもらいましょう。感情的な文書を送れば問題が大きくなります。
(2)「前回の話し合いでは、「〇〇」という話になりましたが、」「〇〇様から前「〇〇」と回答がありましたが、」という形で、前回の話し合いの内容を簡単に要約した上で文書を書き始めましょう。
クレーマーの回答が残っていないと、やりとりを証拠化できないからです。
(3)事情を知らない人が読んでも、その文書だけで中身が分かるように分かるように、経緯(前提事実)から記載しましょう。本題に入る前に経緯(前提事実)から記載しましょう。
クレーマーは、自分の意見を正当化するため専門家に意見を聞きに行きます。こちらの言い分を書いた文書を渡しておけば当該専門家がクレーマーを説得してくれます。
(4)会社としての回答を文書にすることで、チームで対応することができ、社内での方針を共有できます。
(5)口頭で説明する場合も文書の範囲で説明します。文書以外の問題は、後日、検討するということで持ち帰りましょう。このようにすることで、チームで問題に取り組むことができます。
6 クレームを解決しようとしない。
(1)「何も進まない。」ということを話し合いの目的にしましょう。
例えば、「●円を支払うので早く解決してほしい。」と最終的な解決を急ぐと、相手方から「〇〇円にしてくれたら、考えてもよい。」という形で金額がアップしがちです。
(2)クレーマとの話は、ゆっくりと交渉することがセオリーです。
(4)クレーマーから何の連絡もなくなったときそれが解決となります。「解決したのか。」それとも「ただ連絡がないのか分からない。」といった気持ちの悪い解決も多いのが実情です。
(5)クレーマーは最初の3か月ほど、いろいろな要求をしてきますが、それ以上は怒りが続ないようです。その後は1年に1度程度、思い出したのか新たな連絡が来る程度となります。
(6)最初の3か月間は、明らかに不当な要求であっても無視せず、応じられない理由を説明することが大事です。
7 「話を聞く機会は直ちに設ける。」「しかし、回答は即断しない。」
(1)クレーマーから話を聞くアポの設定は、迅速に行う必要があります。
(2)しかし、クレームの対応としては、会社としての回答は即断してはなりません。
(3)あせって、変な約束をすれば、クレームが大きくなります。
(4)「急いで〇〇をやってくれ。」と言われたら、10分間冷静になるために、コーヒーでも飲みましょう。
あせって、対応すれば問題が大きくなります。
8 場所と時間と対応メンバーを検討する。録音する。
(1)クレーマーの家に行って説明するのは論外です。話し合いの場所は、自分たちで用意しましょう。
(2)助けを呼べるかどうか、という問題もあります。時間外でのクレーム対応も論外です。
(3)助けを呼ぶ場合の連絡手段や、待機要員を検討しましょう。
(4)基本的には、一人で対応してはいけません。
(5)対応については、録音しておきましょう。
9 反撃措置を直ぐにとらない。
(1)クレーマーに対して不当要求に関しては、口頭での注意、内容証明、警察への告訴等が考えられます。
(2)しかし、これらの反撃措置はゆっくり、一つずつ段階を上げて行使するのが原則です。
(2)例えば、いきなり刑事告訴してしまうと、その後「刑事告訴するぞ。」と交渉できなくなるからです。