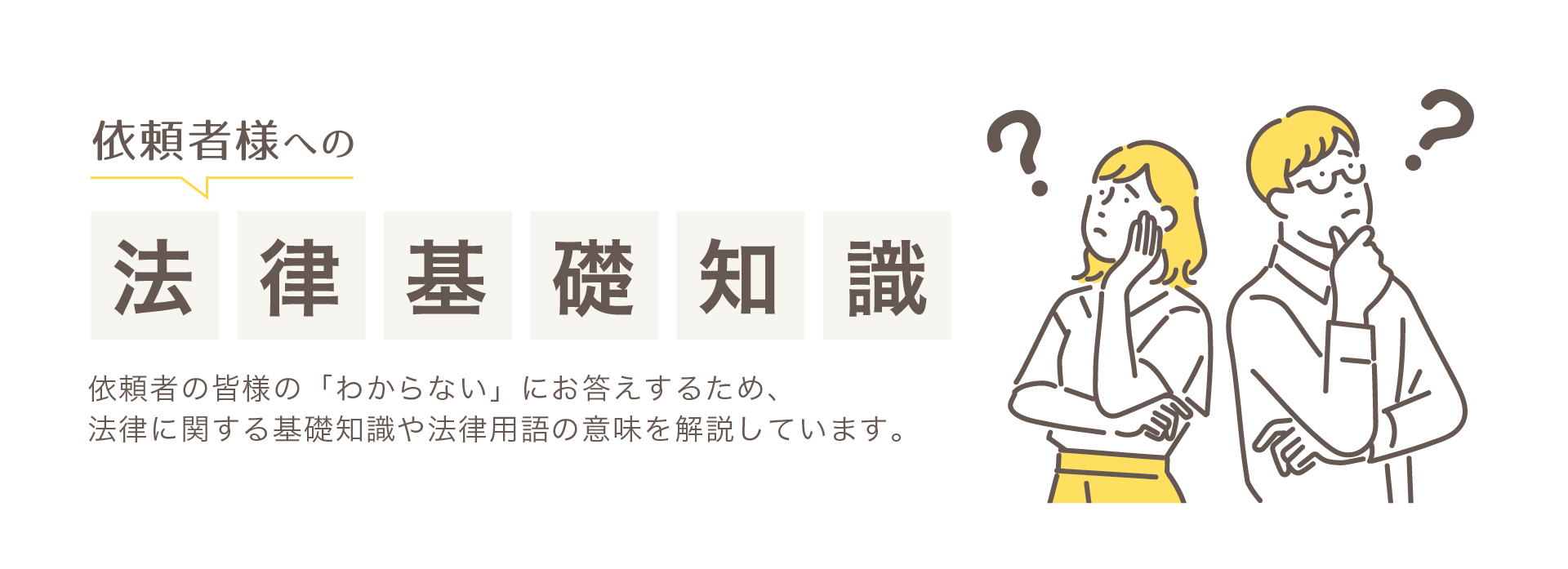判例(システム開発において要件及び仕様に関する合意については、要件定義書や基本設計書により明確化されるのが通常です。そこに書かれていない要件や仕様は追加修正であると推定される。その追加修正によってシステム開発が遅延しても、システム会社に責任はない。)
2025/08/11 更新
このページを印刷システム開発と要件及び仕様の合意
(1) システムの発注ですが、システム会社だけでは作ることはできません。
(2)まず、発注者側で、どのような機能がいるのか明確にしてもらないと作るものが決まりません。
(3)これに対して、発注者はシステム開発のプロではありません。どのように、システム会社に伝えればよいのかは不明です。システム開発では、発注者側にもシステム開発のノウハウがなければ上手くいきません。
要件定義書や基本設計書
(1)システム開発において要件及び仕様に関する合意については、要件定義書や基本設計書により明確化されるのが通常です。そこに書かれていない要件や仕様は追加修正であると推定されます。
(2)したがって、その追加修正によってシステム開発が遅延しても、システム会社に責任はない。
バグと契約解除と代金請求
(1)システム開発について、バグが存在しても、改修によって対応できる場合には債務不履行解除はできません。
請負契約については債務不履行解除が制限されます。既施工部分について(注文者が活用できる出来高部分)については、債務不履行解除できないとされています(最判昭和56年2月17日裁判集民132号129頁)。(建物等の全部解除を認めると、建物を取り壊すほか無くなります。活用できる建物を注文者に買い取らせる方が合理的な解決に向かうからです。)
システム開発も請負契約であります。バグが存在しても、改修によって対応できる場合には債務不履行解除はできません。
(2)注文者が債務不履行解除を主張しシステム開発が中断した場合には、システム開発について途中解除したことになることが多いでしょう(民法641条)。
(3)この場合に、システム会社は、注文者に対し出来高での代金請求をすることになります。
東京高判令和6年1月31日 判例タイムズ1533号90頁
(1)システム開発において要件及び仕様に関する合意については、要件定義書や基本設計書により明確化されるのが通常です。そこに書かれていない要件や仕様は追加修正であると推定されます。
そこに書かれていない要件や仕様は追加修正であると推定される。その追加修正によってシステム開発が遅延しても、システム会社に責任はない。
(2)システム発注者は発注者に対し、「システム会社の担当者の退職や要件整備問題により度重なる仕様変更を要したことが原因である。」という、システム会社の責任を認めるかのような文書を渡している。
しかし、問題が生じた場合に、相手の言い分を認めて謝罪したうえで問題解決を一緒に取り組もうとすることもありえる。システム会社の責任を認める部分については信用性はない。
(3)発注者は、「要件定義書や基本設計書により明確化さていない要件定義についても、その後も検討を重ねて要件定義を明確にしてく合意が存在する。」と主張する。しかし、システム会社に契約(要件定義書や基本設計書の完成)を急ぐ理由もなく、このような合意は認められない。
(4)発注者が契約解除の通知書を送った直後のシステムを復元したシステムで確認すると、発注者が主張するバグはほぼ確認できない。
(5)仮に、発注者の主張するバグが存在しても、改修によって対応できる場合には債務不履行解除はできない。
(6)システム会社は、注文者に対し出来高での代金請求をするができる。
解説
(1)第一審では、システム発注者は発注者に対し「システム会社の担当者の退職や要件整備問題により度重なる仕様変更を要したことが原因である。」という、システム会社の責任を認めるかのような文書を渡していること等が重視され、発注者のシステム会社に対する代金の返還請求が認められました。
(2)第二審では、「問題が生じた場合に、相手の言い分を認めて謝罪したうえで問題解決を一緒に取り組もうとすることもありえる。」とされて、全く逆の判断がされました。
(3)したがって、システム開発のトラブル時にも慎重な対応が求められることを示した示談でもあります。