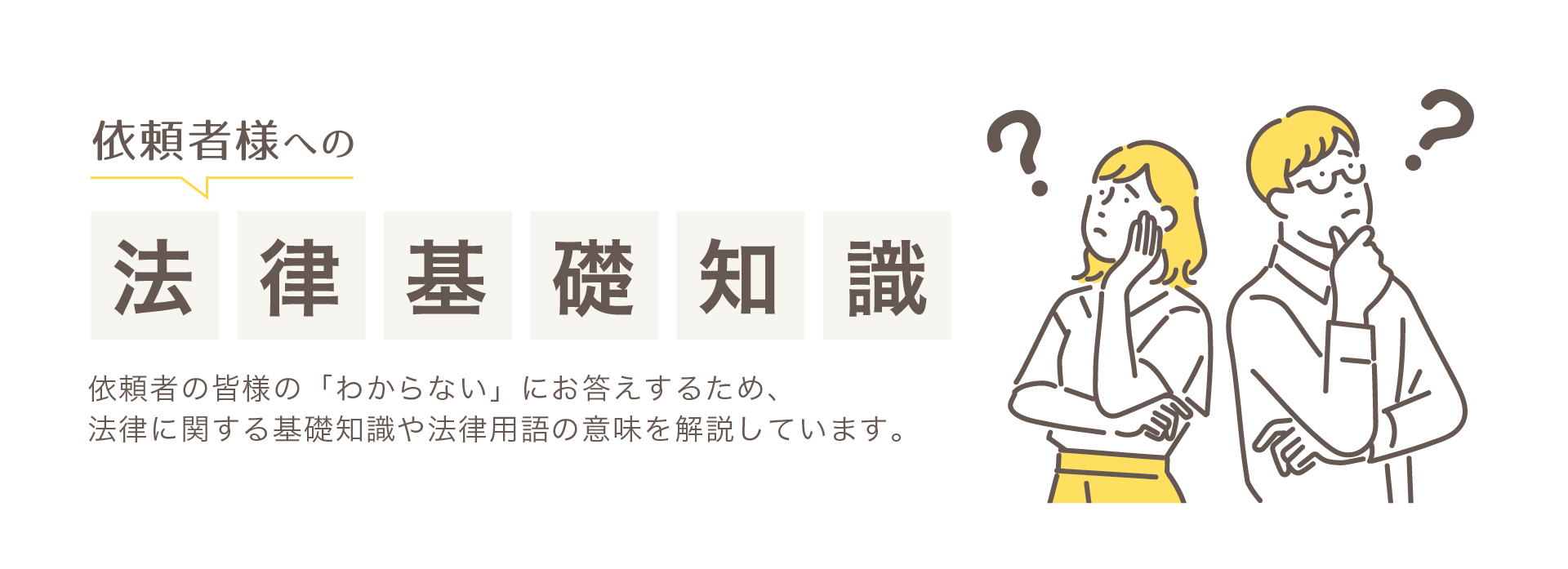判例(特許侵害訴訟の差止請求訴訟で敗訴した被告は、損害賠償請求訴訟において、差止訴訟で主張していなかった特許の無効事由を主張することは許される。)
2025/09/12 更新
このページを印刷判決
特許侵害訴訟の差止請求訴訟で敗訴した被告は、損害賠償請求訴訟において、差止訴訟で主張していなかった特許の無効事由を主張することは許される。
(令和5年2月16日東京地判)
参考
判例タイムズ1523号199頁
特許侵害訴訟と併合
特許侵害訴訟において、原告は差止訴訟と損害賠償請求訴訟を併合して提起することができます。
特許権侵害訴訟においては、特許の侵害の有無と、損害の審理を分けて行う、という運用がされています。
しかし、損害論の審理に時間がかかることも多く、当事者からも、損害賠償請求訴訟はせずに、差止訴訟だけが提起されることがあります。
差止訴訟と損害賠償請求訴訟
特許における差止訴訟と損害賠償請求訴訟が併合提起されている場合には、裁判所が、「特許の侵害が有る。」との心象を示して損害論の審理に移行した場合には、特許の無効事由を主張することは時期に後れたものとなります。
しかし、 時期に後れた攻撃防御方法とは同一訴訟内における攻撃防御方法をいいます。特許における差止訴訟と損害賠償請求訴訟の訴訟物は別である(別の訴訟である)。
原告はあえて、損害賠償請求訴訟はせずに、差止訴訟だけを提起しています。また、被告は訴訟において受け身的に防御活動をする存在です。
したがって、特許侵害訴訟の差止請求訴訟で敗訴した被告は、損害賠償請求訴訟において、差止訴訟で主張していなかった特許の無効事由を主張することは許される、としました。
解説
明示的一部請求については、先行訴訟において、数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決がある場合、原告が残部請求の訴え(後行訴訟)を提起することは特段の事情がない限り、信義則に反して許されない、とされてきました。

明示的一部請求とは、例えば、100万円の支払いの金銭請求について、先行訴訟で(100万円の一部として)50万円、後行訴訟で50万円と分けて訴えを提起するものです。
理論上、先行訴訟と後行訴訟では訴訟物は別ですが、紛争の蒸し返しになるとして、上記の訴えは許されない、とされてきました。
しかし、特許訴訟においては、特許侵害訴訟において被告は、訴訟で応訴するとともに、特許庁において無効審判を請求できます。
この場合に、特許侵害訴訟の差止請求訴訟で敗訴した被告ですが、審判では特許の無効審判を勝ち得て、損害賠償請求訴訟において、これを提出することが考えられます。
したがって、本判決の結論については、知的財産の紛争処理システムが考慮されたものといえます。