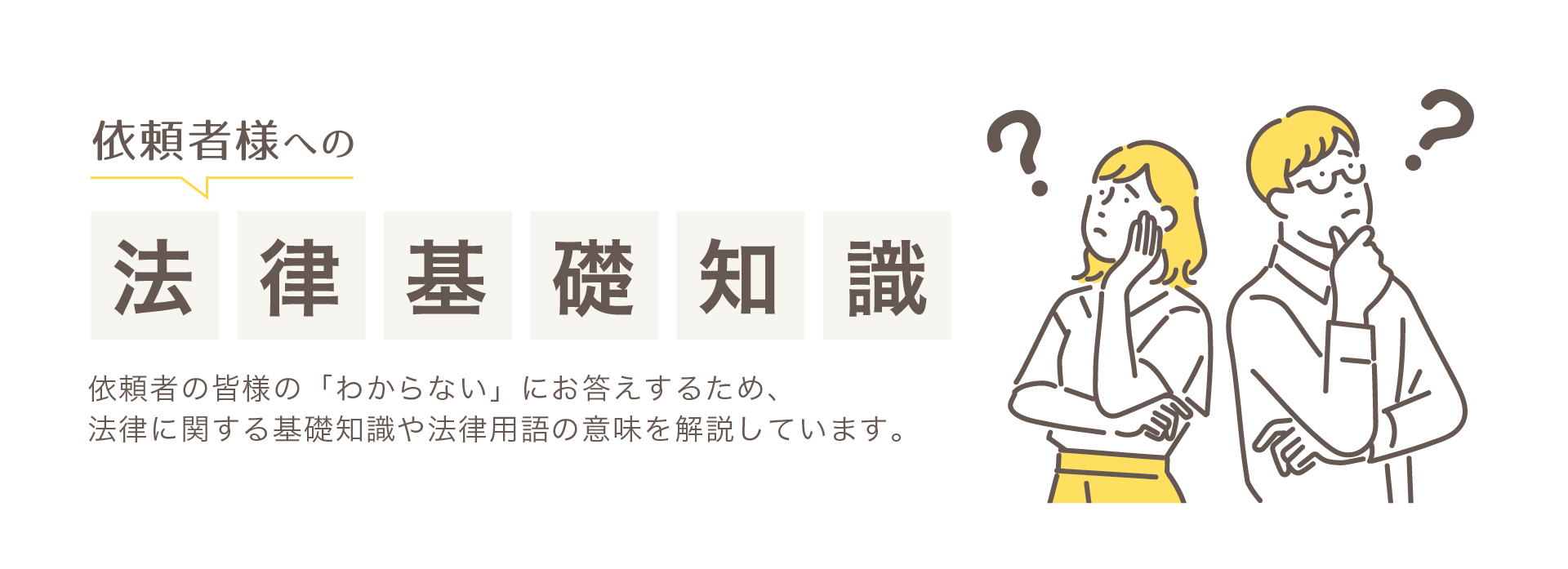判例(胎児認知した者が、その子は自分とは別の子の嫡出子であることが明らかであるとして、胎児認知無効確認請求をしたことが権利の濫用にあたるとされた。)
2025/04/25 更新
このページを印刷認知制度
婚姻関係外で、生まれた子を非嫡出子といいます。
母親と子は出産によって親子関係が明確になります。しかし、父親と子の親子関係は簡単に決まりません。
婚姻関係中に、生まれた子は嫡出推定等で、父子関係が決まります。これに対して、婚姻関係外で、生まれた子については認知の問題となります。
仮に、認知した親子関係について争う場合には、親子関係不存在の訴えを提起することになります。
また、認知無効の訴えを提起することも考えられます。
| 民法786条 (認知の無効の訴え) 1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。 一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時 二 認知をした者 認知の時 三 子の母 子の母が認知を知った時 2項 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。 3項 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。 4項 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。 |
東京家裁令和5年3月23日
判決
裁判所は、以下の事情から、父親(児認知した者)が、その子は自分とは別の子の嫡出子であることが明らかであるとして、胎児認知無効確認請求をしたことが権利の濫用にあたるとしました。
(1)認知した者は、「Bが子の父である。」と主張するが、Bが子の父として認めれる可能性が乏しいこと(したがって、子の父がいなくなること
(2)認知した者が子の生物学上の父であることを争っていないこと
(3)認知した者は、母とBの婚姻期間中に懐胎した子であると認識しながら胎児認知の届出をしたと推認されること
(4)認知した者が子に対し、父として接してきていたこと
(5)子が日本国籍を喪失するなど過酷な状況に置かれる可能性があること
参考
判例タイムズ1529号251頁
解説
(1)最三小判平26・1・14民集68巻1号1頁、判夕1403号80頁は、「認知無効確認請求は、権利濫用にあたることがある。」ことを認めていましたが、どのような事情があれば、権利濫用になるのか不明確でした。
(2)本判決は、どのような事案で権利濫用と判断されるのか、一例を示したものとなります。