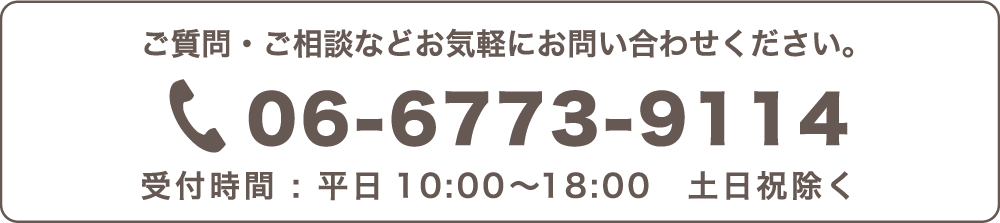【労働条件通知書】労基法と、労働条件通知書の記載
2025/03/27 更新
労働条件通知書
(1)従業員を雇用したときには、労働条件通知書を交付しなければなりません。
(2)労働基準法は、①期間と更新の基準、②就労の場所、業務の内容、③労働時間、出勤日、休日、④賃金、⑤退職、解雇を記載しなければならないと定めている(労基法15条1項)。
(3)労働条件通知書の記載は法令にそった内容でなければなりません。つまり、各記載について法令を理解していることが必要になります。
①期間と更新の基準
(1)有期雇用とは、3か月~1年間等一定期間に限り雇用する期限付きの雇用契約であります。
(2)有期雇用にする場合には、雇用条件通知書にて、雇用期間(3か月~1年間等)を記載することが必要です。
①雇用期間
「期間の定め無し」とするか、「雇用の期間(例えば、令和5年3月1日~ 令和5年7月末日までとする)」を記載しなければなりません。
②更新の有無と更新についての基準
(1)有期雇用とした場合に、「契約の更新をしないのか。」それとも、「契約の更新をする場合があるのか。」を記載します。
(2)「契約の更新をする場合がある」ときには、どのような要素を考慮して、更新をするのかを、を記載します。
具体的には、「業務量、勤務態度、勤務成績、会社の経営状態、従事している業務の進捗、これらと同様に重要な事実を考慮して、契約更新をするかどうか、を決める。」と記載しておけば大丈夫です。
③更新の上限
(1)令和6年4月1日により、有期雇用について、通算契約期間(通算契約期間は3年とする)や更新回数(更新は3回まで)の条件を定める場合には、その旨を雇用条件通知書に記載する義務があります(労働基準法施行規則の改正)。
(2)令和6年4月1日により、有期雇用について、初回の契約時には、更新上限を設けていなかったが、その後に更新上限を設ける場合や、期間等を引き下げる場合には、上限を設ける前にその理由を説明しなければならなくなりました(有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)の改正)。
参考
ビジネスガイド2024年2月号6頁
④無期転換権
(1)更新を繰り返し、契約期間が通算して5年を超えると、期限の定めのない無期雇用に変更してほしいと請求する権利が発生します。これを無期転換申込権といいます(労働契約法18条)。
(2)5年を超えて契約を更新する場合には無期転換権が発生します。令和6年4月1日により、無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込権が発生します。」等の記載が必要です(労働基準法施行規則の改正)。
(3)以下のように、契約終了時において無期転換請求権が発生しない場合には、無期転換申込権について記載する必要はありません。
| 定年後再雇用 | 有期雇用特別措置法 定年後引き続いて雇用される従業員については、有期雇用特別措置法の特定の手続をすれば、無期転換権が発生しません。 この場合には、無期転換申込権の記載は不要です。 |
| 更新の上限 | 更新の上限 契約更新の上限を設ける場合には、有期雇用の契約期間を通算契約期間(通算契約期間は5年以内とする)や更新回数(更新は5回までとする)との条件を定める場合には、契約期間が通算して5年を超えませんので、無期転換申込権は発生しません。 この場合には、無期転換申込権の記載は不要です。 |
| 契約終了時が初期契約から5年以内となるとき | (1)5年を超えて契約を更新する場合には無期転換権が発生します。令和6年4月1日により、無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込権が発生します。」等の記載が必要です(労働基準法施行規則の改正)。 (2)例えば、1年契約の有期雇用を締結した1年目の雇用条件通知書については、その契約終了日に無期転換申込権は発生しません。 この場合には、無期転換申込権の記載は不要です。 |
⑤無期転換申込権の記載のポイント
(1)この契約(書)について無期転換申込権を記載すべきかどうか、管理するためには、「(初期契約日 令和 年 月 日、同日から5年間を経過した日の翌日から無期転換を申し込める。)」と記載する方法が分かりやすいでしょう。
(2)少なくとも、「(初期契約日 令和 年 月 日)」の記載欄を作っておきましょう。
⑥契約期間その他記載例
| 契約期間 | ( )期間の定めなし 令和 年 月 日~ (〇)期間の定めあり (令和6年4月1日 ~ 令和7年3月末日) |
| 契約更新の1有無 更新の上限と、無期転換申込権 | ( )更新しない (〇)更新する更新する場合がある。更新する場合には、契約期間満了時の業務量、勤務成績、態度、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況を考慮する。 (〇)更新の上限あり。(更新 回まで/通算期間5年) 無期転換申込権が無し ( )更新の上限なし。 無期転換申込権あり。(初期契約日 令和 年 月 日、同日から5年間を経過した日の翌日から無期転換を申し込める。) |
②就労場所、業務内容
(1)雇用条件通知書に、就労する場所や、業務の内容を記載しなければなりません。
(2)令和6年4月1日により、入社時の就労場所と、入社時の業務内容、就労場所の変更範囲、業務内容の変更範囲を記載することが必要です(労働基準法施行規則の改正)。
(3)入社後、就業場所や、業務内容が変更になる場合があります。そこで、変更の範囲を記載することが必要です。
| 業務内容 | 入社時 事務一般 変更範囲 全ての業務 |
| 就労場所 | 入社時 大阪営業部 変更範囲 リモートワークや、全ての支店(全国の支店を含む) |
③労働時間、出勤日、休日
所定労働時間
(1)所定労働時間は、会社が定めた労働時間のことをいいます。
(2)所定労働時間は法定労働時間内でなければならない。法定労働時間以上働かせることが必要であるときには、36協定の提出が必要になります(労働基準法36条)。
| 休憩時間 営業時間9時から20時までの間に、シフトで1時間休憩をとる。 勤務時間 営業時間9時から20時までの間の8時間として、シフトで決める。 出勤日・休日 会社のシフトで週に2日の休みを設ける。 という記載もOKである。法律の要件を満たす記載が必要である。 |
法定労働時間
法定労働時間は1日8時間、週40時間が原則です(労働基準法32条1項)。
もっとも、常時10人未満の労働者を使用する特例措置対象事業場の週の法定時間は44時間であります(特例措置対象事業場)。
| (1)特例措置対象事業場の法定労働時間は、1日8時間、1週44時間であります。 (2)特例措置対象事業場は、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場です。 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)。 映画・演劇業(映画の映写(映画の製作の事業を除く)、演劇、その他興業の事業)。 保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)。 接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。 (3)特例措置対象事業場にあたるかどうかについて、事業場の労働者の数は企業全体で数えるのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場において雇用される労働者の数を基準にします。 |
休憩時間
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条1項)。
休日
一週間に1日の休日を与えるか、もしくは、4週間を基準に4日以上の休暇を与えなければなりません(労働基準法35条)。
年次有給休暇
(1)6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には10日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条1項)。
(2)労働時間(パートタイム)や勤務年数で付与される有給休暇の日数は変わってきます。
⑤退職、解雇
定年
(1)雇用条件通知書に、定年の有無と、定年の年齢を記載する必要があります。
(2)退職日については、定年の年になった日(法律上は誕生日の前日)とするのか、それとも、定年の年になった日(法律上は誕生日の前日)の属する月末とするのかを記載します。
継続雇用制度
(1)高年齢者雇用安定法は、①定年を65歳まで引き上げること、②定年後65歳まで引き続き雇用すること(継続雇用制度)、③定年制を廃止すること、のいずれか3点の措置を採ることを求めています。
(2)なお、継続雇用制度等を採用する場合には、定年後の全ての労働者を再雇用しなければなりませんが、定年後の労働条件に関して賃金を下げたり、出勤日を少なくしたりして給料を下げることは認められています。
(3)なお、企業が①②③の義務を怠ったとしても、同企業と定年後退職者との間に雇用契約が成立するわけでありません。あくまで、雇用契約の内容は企業と労働者の間で詳細を決めなければ成立しえないからです。つまり、同法の違反はあくまで行政の指導の対象になるにすぎません。そのため、継続雇用制度の導入をわざと見送っている中小企業もあります。
(4)雇用条件通知書に、継続制度の有無を記載する必要があります。
自己都合退職のルール
(1)雇用条件通知書に、労働者側から退職の申し出をするのに●日以前に届け出ることと、退職のルールを記載する必要があります。
(2)法律上は、期間の定めのない雇用契約に関し、労働者は退職の申し出をすれば2週間で退職できると決まっています(民法627条1項)。
| 「従業員が退職するさいには1か月前に届け出なければならない」と記載しても、違法無効です。しかし、労働条件通知書そのもの(有期雇用であることや、固定残業の導入その他)が無効になるわけでもありません。 |
解雇のルール
(1)雇用条件通知書に解雇のルールを記載する必要があります。
(2)解雇事由を記載する必要があります。
具体的には、「継続的な勤務態度の不良、継続的な勤務成績の不良、会社の経営状態の悪化、従業員の犯罪行為、不法行為、その他、解雇を正当化する事由がある場合には、会社は従業員を解雇できる。」と記載しておけば大丈夫です。
(3)解雇予告手当について記載する必要が有ります。
具体的には、「会社が従業員を解雇する場合には、30日前に予告しない限り解雇予告手当の支払い義務を負う。なお、労働基準監督署の除外認定を受けた場合にはその限りでない。」と記載しておけば大丈夫です。
なお、「詳細は就業規則の定めによる」として省略することも可能です。
社会保険
(1)社会保険は、従業員の関心の高い問題です。
(2)法律上の義務はありません。しかし、雇用条件通知書には、社会保険についても記載するのが通常です。
労働保険
(1)雇用保険・労災保険をあわせて労働保険といいます。
(2)①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険をかけなければならないのが原則です。
社会保険
厚生年金・健康保険を合わせて社会保険といいます。
①適用事業所
以下の事業所は、社会保険(厚生年金)の適用事業所となります。
(ア)すべての法人(事業主のみの場合を含む)
(イ)従業員が常時5名いる個人事業主の特定の事業の事業所(農林水産業、飲食店業、サービス業以外の事業所)
②被保険者
社会保険(厚生年金)の適用事業所において、通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上ある労働者には、社会保険をかけなければなりません。
| 法人化した場合従業員を1名も雇用してなくても、社長は社会保険に加入しなければならない。 |
| 以下の要件を満たす場合には、労働者には、社会保険をかけなければなりません。 ①雇用保険の適用事業所であること ②週労働時間が20時間以上 ③賃金月額が月8.8万円以上 ④勤務期間が2ヶ月以上の見込み ⑤学生でないこと ⑥「(厚生年金の被保険者である)従業員が101名以上」もしくは、「任意適用事業所であること」 |
相談窓口
(1)パートタイム・有期雇用労働法により、有期雇用の労働者・短時間労働者(パートタイム労働者)から求めがあれば、労働条件通知書に、相談窓口を記載する必要があります。
(2)正社員に相談窓口を記載しても間違いではない。ややこしいので、全て相談窓口を記載してもよいだろう。